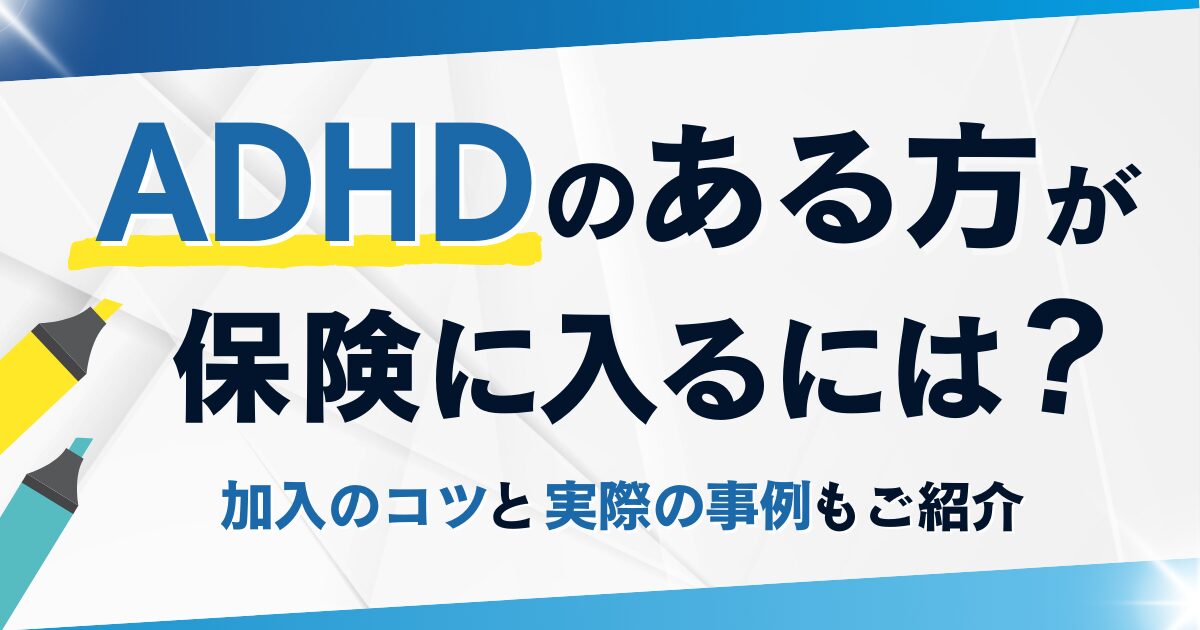K太さん
K太さん「ADHD(注意欠如・多動症)と診断されたけれど、保険には入れるのだろうか…」




「保険の告知では、何をどこまで伝えればいいのだろう…」




「子どもの将来や自分の万が一を考えると不安だけど、どんな保険を選べばいいのかさっぱりわからない…」
ADHDのある方やそのご家族にとって、保険に関する悩みは尽きません。
日常生活では、集中力の維持が難しかったり、衝動的に行動してしまったりすることで、ケガや事故のリスクを心配される方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そんなADHDのある方やご家族の皆さんが抱える保険の悩みに真正面から向き合い、解決のための一歩を踏み出すお手伝いをします。
この記事を読むことで、以下のことがわかります。
- ADHDと保険に関する基本的な知識が身につきます。
- ADHDがあっても加入しやすい保険の種類や、告知の際の具体的な注意点がわかります。
- 国の公的な制度と民間の保険を上手に組み合わせて、賢く備える方法が理解できます。
- 実際に保険に加入できた方や、保険金請求で助かった方の具体的な事例を通して、自分に合った保険選びのヒントが得られます。
結論 ADHDと診断されても保険に加入できることがあります
ズバリ、ADHDと診断されていても、保険に加入できることがあります!
保険会社は、ADHDの特性や現在の状況、治療によるコントロール状態などを総合的に見て、加入できるかどうかを判断します。
大切なのは、「告知義務(こくちぎむ)」をきちんと果たすこと、つまり健康状態や病歴について正直に保険会社に伝えることです。
そして、ご自身やご家族の状況に本当に合った保険を選ぶことが、将来の安心を守るための最も重要な鍵となります。




ADHDの特性を理解した上で、あなたやあなたの大切なご家族にぴったりの「安心」を見つけるお手伝いができれば幸いです。
ADHDと保険加入について



ADHDと保険の関係について、もう少し詳しく見ていきましょう。
なぜADHDであることが保険加入に関係するのか、保険会社はどのように考えているのか、そしてなぜ「告知義務」がそれほど重要なのか。
これらの理由と根拠を理解することで、保険選びがよりスムーズに進められるはずです。
ADHD(注意欠如・多動症)とは
まず、ADHD(注意欠如・多動症)について簡単におさらいしましょう。
大切なのは、ADHDは「病気」ではなく、生まれ持った脳の機能の「特性」であるということです。
そのため、一人ひとり症状の現れ方や困りごとは異なります。
例えば、日常生活では計画を立てて物事を進めるのが苦手だったり、感情のコントロールが難しかったりすることがあります。
厚生労働省の調査によると、医師から発達障害と診断される人の数は年々増加しており、令和4年(2022年)の調査では、その推計数は約87万2千人にのぼると報告されています。
厚生労働省:令和4年生活のしづらさなどに関する調査 (全国在宅障害児・者等実態調査)結果の概要(P5)
これは、発達障害に対する社会的な理解が深まってきたことも一つの要因と考えられます。
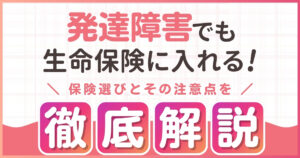
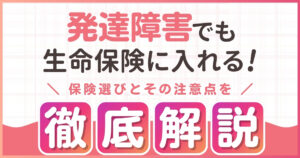
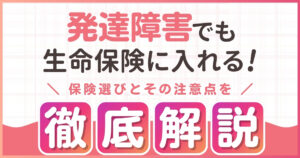
保険会社はADHDをどう見ている?
次に、保険会社がADHDをどのように捉えているのか、保険加入の審査という観点から見ていきましょう。
保険は、基本的に「相互扶助(そうごふじょ)」という助け合いの精神で成り立っています。
多くの人が少しずつ保険料を出し合い、誰かが病気やケガ、あるいは万が一の事態に陥ったときに、集まった保険料から保険金や給付金が支払われる仕組みです。
そのため、保険会社は加入者全体の公平性を保つ必要があります。
特定の加入者だけが保険金を受け取る確率が著しく高いと判断される場合、他の加入者との間で不公平が生じてしまうため、以下のような対応がとられることがあります
公平性を保つための保険会社の対応
- 保険料を通常より高く設定する(割増保険料)
- 特定の病気や部位を保障の対象外とする(特定疾病・部位不担保)
- 場合によっては加入を断る
では、ADHDの場合、保険会社はどのようなリスクを考慮するのでしょうか。
- ADHDの特性によるリスク
不注意や衝動性といった特性から、ケガや事故に遭うリスクが他の人よりも高いのではないかと判断されることがあります。 - 二次障害のリスク
ADHDのある方は、ストレスなどからうつ病や不安障害といった他の精神疾患を併発する(二次障害)可能性が指摘されています。
これらの精神疾患は治療が長期化する傾向があるため、保険会社にとってはリスク要因となり得ます。
しかし、大切なのは、保険会社はADHDだからという理由だけで、一律に保険加入を断るわけではないということです。症状の程度、治療によるコントロール状況、日常生活への支障の度合いなどを総合的に見て、個別に判断します。
告知義務の重要性
保険に加入する際に最も重要なことの一つが「告知義務(こくちぎむ)」です。
これは、保険に申し込む人が、自分の過去の病歴や現在の健康状態などについて、保険会社に正確に、ありのままに伝える義務のことです。
ADHDの何をどこまで伝えるべきか?
ADHDと診断されている場合、またはその疑いで通院している場合は、主に以下の情報を告知する必要があります。
- 診断名
ADHDであること(または疑いがあること) - 初診日・診断日
いつ初めて医師の診察を受けたか、いつ診断されたか - 治療内容・期間
これまでの治療内容(カウンセリング、薬物療法など)や治療期間 - 服薬状況
服用している薬の名前、量、頻度など - 現在の症状の程度
日常生活や社会生活(学業や仕事など)にどの程度支障が出ているか
FPとしては、医師の診断書やこれまでの治療経過をまとめたメモなどを準備し、正確に伝えることをお勧めします。




何をどう伝えたらいいのかわかるか心配だなぁ。




もし、何をどこまで告知すればよいか不安な場合は、正直に保険会社やFPに相談しましょう。
告知義務違反のリスク
もし、告知すべき内容を故意に伝えなかったり、事実と異なることを伝えたりした場合、それは「告知義務違反」となり、以下のような重大な結果を招く可能性があります。
- 保険契約の解除
保険会社は契約を解除することができます。 - 保険金・給付金が支払われない
いざという時に、保険金や給付金が一切支払われないことがあります。
例えば、過去の裁定事例では、広汎性発達障害の疑いで通院していた事実を告知しなかったために、保険契約が解除されたケースがあります。
本人が「発達障害は病気ではない」と考えていたとしても、医師の診察や検査を受けている状態であれば、告知義務の対象となります。
ADHDと診断されている方やそのご家族が、「発達障害は病気ではないから告知しなくても大丈夫だろう」と安易に自己判断してしまうと危険です。
保険加入後にADHDと診断された場合は?
原則として、保険に加入した後にADHDと診断された場合、そのことを新たに保険会社に告知する義務はありません。
ただし、新たに別の保険に加入する際や特約を追加する際には、その時点での健康状態を正確に告知する必要があります。
ADHDの方における保険の必要性
ADHDの特性を考えると、以下のようなリスクに備えるために保険の必要性が高まることがあります。
- ケガや事故のリスク
不注意や衝動性から、日常生活で思わぬケガをしたり、事故に遭ったりする可能性が考えられます。 - 個人賠償責任のリスク
注意不足や衝動的な行動によって、他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりするリスクです。場合によっては高額な損害賠償を請求されることもあります。 - 二次障害による就業困難のリスク
ADHDのある方は、ストレスなどからうつ病などの二次的な精神疾患を併発することがあり、それによって長期間働けなくなるリスクも考慮に入れる必要があります。




「ADHDの特性を理解した上で、まずは公的な制度を最大限に活用し、それでもカバーしきれないリスクに対して、民間の保険で賢く備えることが大切です。
ADHDの方が加入しやすい保険とは?



ADHDと診断されていても、加入を検討できる保険はいくつかあります。
ここでは、代表的な保険の種類と、ADHDのある方が加入する際のポイントや注意点を、詳しくご紹介します。
ADHDの方が検討しやすい保険種類一覧
| 保険種類 | 主な特徴 | ADHDの方の加入ポイント | メリット | デメリット |
| 医療保険 | 病気やケガによる入院・手術費用などを保障 | 診断名、治療状況、日常生活への支障の程度などを正確に告知。症状が安定していれば通常タイプも可能性あり。 | 万が一の入院や手術に備えられる。 | 症状によっては加入が難しかったり、保険料が割増になる場合がある。 |
| 生命保険(死亡保険) | 被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に保険金支払い | 症状が軽度で日常生活に支障がなければ比較的加入しやすい。 | 万が一の際に家族の生活を守れる。 | 告知内容によっては加入が難しい場合がある。 |
| がん保険 | がんの診断、入院、手術、通院などを保障 | ADHDとがんの直接的因果関係は薄いため比較的加入しやすい。告知もがん関連が中心。 | がん治療の経済的負担を軽減できる。 | がん以外の病気やケガは保障されない。 |
| 就業不能保険・所得補償保険 | 病気やケガで長期間働けなくなった場合の収入減少を補う | 精神疾患(二次障害含む)は対象外か条件付きが多い。加入が難しい傾向。 | 働けなくなった時の収入をカバーできる。 | 精神疾患は対象外か条件付きが多い。加入が難しい場合がある。 |
| 引受基準緩和型保険 | 健康状態の告知項目が少なく、持病があっても加入しやすい | ADHDの診断があっても、告知項目に該当しなければ加入しやすい。 | 持病があっても加入しやすい。 | 保険料が割高、保障削減期間がある、特約が少ない場合がある。 |
| 個人賠償責任保険 | 日常生活での対人・対物事故による損害賠償を補償 | ADHDの特性による事故リスクに備える。健康状態の告知は不要な場合が多い。 | 比較的少ない保険料で高額な賠償リスクに備えられる。 | 補償範囲や免責事項の確認が必要。 |
| 共済 | 組合員同士の助け合い制度。掛金が割安な場合が多い | 加入基準が緩やかな場合がある。発達障害専門の共済も。告知義務はある。 | 掛金が割安な場合が多い。発達障害専門の共済もある。 | 保障内容がシンプル、死亡保障が低い、保険料控除対象外の共済もある。 |
医療保険
病気やケガによる入院費用や手術費用などを保障してくれるのが医療保険です。
ADHDのある方が医療保険に加入する際には、以下の点を正確に告知することが求められます。
- 診断名(ADHDであること)
- 治療状況(通院の頻度、服薬している薬の種類や量など)
- 日常生活への支障の程度
保険会社は、これらの情報をもとに、将来的な入院リスクなどを総合的に判断します。
症状が安定しており、日常生活に大きな支障がないと判断されれば、通常の医療保険に加入できる可能性もあります。
しかし、入院リスクが高いと判断されると、加入が難しくなったり、特定の条件(保険料の割増や特定部位不担保など)が付いたりすることがあります。
メリットとしては、万が一の入院や手術の際に高額になりがちな医療費の自己負担を軽減できる点です。
デメリットとしては、ADHDの症状や状態によっては加入のハードルが高かったり、保険料が割高になったりする可能性がある点です。
生命保険(死亡保険)
生命保険は、被保険者(保険の対象となる人)が亡くなった場合や、所定の高度障害状態になった場合に、保険金が支払われる保険です。
残されたご家族の生活費や、ご自身の葬儀費用などに備える目的で加入を検討します。
ADHDのある方の場合、症状が比較的軽度で、日常生活に大きな支障がなければ、生命保険に加入しやすい傾向があります。
しかし、ADHDの特性である衝動性などから、不慮の事故に遭うリスクが高いと保険会社が判断した場合には、加入が難しくなることもあります。
メリットは、万が一のことがあった際に、残された家族の経済的な負担を大きく軽減できる点です。
デメリットは、告知内容によっては加入が難しくなる場合がある点です。
がん保険
がん保険は、がんと診断された場合や、がんによる入院・手術・通院などに対して保障が受けられる保険です。
ADHDとがんの発症率に直接的な医学的因果関係は認められていないため、ADHDと診断されていても、がん保険には比較的加入しやすいと言われています。
告知項目も、主にがんに関連する病歴や健康状態が中心となります。
メリットは、治療費が高額になることもあるがん治療に対して、経済的な備えができる点です。
デメリットは、がん以外の病気やケガについては保障されない点です。
就業不能保険・所得補償保険
病気やケガで長期間働けなくなった場合に、収入の減少を補ってくれるのが就業不能保険や所得補償保険です。
しかし、残念ながら、ADHDと診断されている方がこれらの保険に加入するのは難しいケースが多いのが現状です。
多くの就業不能保険では、精神疾患(ADHDの二次障害として起こりうるうつ病なども含む)を保障の対象外としていたり、対象となる場合でも入院や特定の状態が条件であったり、給付期間に制限があったりします。
FPとしては、ADHDの方が働けなくなった時の備えとして、まずは国の公的保障である「障害年金」をしっかりと理解し、活用することを第一に考えることをお勧めします。
その上で、民間の保険で補いたい部分があれば、加入が比較的しやすい損害保険会社が扱う「所得補償保険」などを検討してみるのも一つの方法です。
メリットは、働けない期間の収入を補填できる点です。
デメリットは、ADHDの方は加入のハードルが非常に高く、精神疾患が保障対象外となる商品が多い点です。
引受基準緩和型保険(限定告知型保険)
「通常の保険には入れそうにないけれど、どうしても何らかの備えが欲しい…」という場合に検討できるのが、引受基準緩和型保険(ひきうけきじゅんかんわがたほけん)です。
これは、健康状態に関する告知項目を少なくしたり、審査の基準を緩やかにしたりすることで、持病や過去に病気をしたことがある方でも加入しやすく設計された保険です。
告知項目は、
- 「過去〇ヶ月以内に入院や手術を勧められたか」
- 「過去〇年以内に入院・手術をしたか」
- 「過去〇年以内に特定の病気(がんなど)で治療を受けたか」
といった、いくつかの簡単な質問に「はい」か「いいえ」で答える形式が一般的です。
ADHDと診断されていても、これらの告知項目に該当しなければ、加入できる可能性が高まります。
メリットは、持病があっても加入しやすい点です。
デメリットとしては、以下の点が挙げられます
- 保険料が通常の保険よりも割高になることが多い
- 加入してから一定期間(例えば1年間)は、受け取れる保険金や給付金が半額などに減額される「支払削減期間」が設けられている場合がある
- 選べる特約の種類が少ないことがある
FPとしては、「引受基準緩和型保険は、保険料が割高になる傾向はありますが、どうしても保険に入りたい場合の有効な選択肢です。
複数の商品を比較し、保障内容と保険料のバランス、特に支払削減期間の有無や内容をよく確認しましょう」とお伝えします。




ADHDの二次障害としての精神疾患を心配される場合は、その精神疾患が保障対象外となっていないかも確認が必要です。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、日常生活の中で、誤って他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害を補償してくれる保険です。
ADHDの特性である不注意や衝動性から、思わぬ事故を起こしてしまうリスクに備えるために有効な保険と言えます。
例えば、
- 自転車で人にぶつかってケガをさせてしまった
- お店の商品を誤って壊してしまった
といったケースが考えられます。
多くの場合、自動車保険や火災保険の特約として付帯できたり、クレジットカードのサービスとして付いていたりします。
単独で加入できる商品もあります。
健康状態に関する告知は不要な場合が多いのも特徴です。
メリットは、比較的少ない保険料で、時に数千万円にもなる高額な賠償リスクに備えられる点です。
デメリットとしては、補償される範囲(例えば、同居の家族全員が対象か、など)や、保険金が支払われないケース(免責事項:例えば仕事中の事故は対象外など)をしっかりと確認する必要がある点です。




「ADHDのお子さんがいらっしゃるご家庭や、ご自身がADHDで不注意による事故が心配な方には、特に検討をおすすめしたい保険です。
過去には自転車事故で1億円近い賠償命令が出た事例もあります。
個人賠償責任保険は、ADHDの特性から生じうるリスクと直接的に関連性が高く、非常に重要な備えとなり得ます。
特にお子さんの場合、親の監督責任が問われるケースもあるため、家族全員をカバーするタイプが望ましいでしょう。
個人年金保険
個人年金保険は、将来の老後の生活資金を計画的に準備するための貯蓄型の保険です。
ADHDのある方にとって、告知が比較的緩やかな商品もあるため、選択肢の一つとなり得ます。
また、一定の条件(契約者と年金受取人が本人またはその配偶者であること、保険料の払込期間が10年以上であることなど)を満たせば、支払った保険料が「個人年金保険料控除」の対象となり、所得税や住民税が軽減される税制優遇を受けられる場合があります。
ADHDの特性上、長期的な計画を立てたり、お金の管理をしたりするのが苦手な方もいらっしゃるかもしれません。
個人年金保険は、毎月自動的に保険料が引き落とされるため、半強制的に老後資金を準備できるというメリットがあります。
ただし、iDeCo(個人型確定拠出年金)など、他の老後資金準備制度と比較して、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です」とお伝えします。
メリットは、計画的に老後資金を準備できる点や、生命保険料控除による節税効果が期待できる点です。
デメリットとしては、物価上昇(インフレ)によって将来受け取る年金の価値が目減りするリスクがある点、iDeCoと比較して税制優遇が小さい場合がある点、途中で解約すると元本割れする可能性がある点などが挙げられます。
公的制度の賢い活用法



民間の保険を検討する前に、まずはADHDのある方が利用できる公的な制度について知っておくことが非常に重要です。
これらの制度を最大限に活用し、それでも足りない部分を民間の保険で補うのが、賢い備え方と言えるでしょう。
ADHDの方が利用できる可能性のある公的制度一覧
以下に、ADHDのある方やそのご家族が利用できる可能性のある主な公的制度をまとめました。
詳細な条件や申請方法は、お住まいの自治体や各制度の公式サイトで必ず確認してください。
| 制度名 | 概要 | 主な対象者 | 受けられる支援・メリット | 申請窓口 |
| 障害年金 | 病気やケガで生活や仕事が制限される場合に支給される年金。ADHDも対象。 | 初診日に年金に加入し、保険料納付要件を満たし、障害等級に該当する方。 | 等級に応じて年金が支給される。 | 日本年金機構、お住まいの市区町村の年金窓口、年金事務所。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害のある方が福祉サービスを利用するための証明書。ADHDも対象。 | 精神疾患があり、日常生活に長期の困難や制限がある方。 | 税金の控除・減免、公共料金の割引、障害者雇用枠での就労など。 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口。 |
| 療育手帳(知的障害を伴う場合) | 知的障害のある方が支援を受けるために必要な手帳。 | 児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方。 | 各種福祉サービス、支援。 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、児童相談所、知的障害者更生相談所。 |
| 自立支援医療制度(精神通院医療) | 精神疾患の通院医療費の自己負担を軽減する制度。ADHDも対象。 | 精神疾患で継続的な通院医療が必要な方。 | 医療費の自己負担が原則1割に軽減。所得に応じ月額負担上限額設定。 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口。 |
| 特別児童扶養手当 | 20歳未満で精神または身体に障害のある児童を監護する父母等に支給。 | ADHDを含む発達障害により、一定以上の障害の状態にある児童を養育している方。所得制限あり。 | 障害の程度に応じて手当が支給される。 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口。 |
| 障害児福祉手当 | 20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害児に支給。 | ADHDを含む発達障害により、重度の障害があり常時介護が必要な20歳未満の方。所得制限あり。 | 月額で手当が支給される。 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口。 |
| その他 | 傷病手当金(会社員・公務員)、生活福祉資金貸付制度、生活困窮者自立支援制度、医療費控除、障害者控除など。 | 各制度の要件による。 | 各制度による。 | 各制度の担当窓口、国税庁(医療費控除・障害者控除)など。 |
公的制度と民間保険の組み合わせ方
ADHDのある方やそのご家族にとって、経済的な不安を軽減するためには、公的制度と民間の保険を上手に組み合わせることが非常に大切です。
公的保険を最大限使う
日本の公的医療保険制度は手厚く、多くの場合、医療費の自己負担は3割(年齢や所得によって異なります)です。
さらに、高額な医療費がかかった場合には「高額療養費制度」があり、自己負担額には上限が設けられています。
ADHDの治療で精神科に通院する場合、「自立支援医療制度(精神通院医療)」を利用すれば、自己負担が原則1割に軽減されます。




これらの公的制度でカバーしきれない部分や、さらに手厚い保障を求める場合に、民間の保険を検討するのが賢明な方法です。
予算が限られている場合の優先順位
もし予算が限られている場合は、以下の順番で優先順位を考えてみましょう。
- 医療費の備え
- 公的医療保険(健康保険)と自立支援医療制度をまず活用します。
- それでも不足する可能性のある費用(例:入院時の差額ベッド代、先進医療の技術料、通院にかかる交通費など)を、民間の医療保険で補うことを検討します。
ADHDの方は、引受基準緩和型医療保険が選択肢に入ることが多いでしょう。
- 万が一の生活保障(死亡・高度障害・就業不能)
- 障害年金や遺族年金といった公的年金が基本的な保障となります。
- もし働いていて収入がある場合は、就業不能保険や所得補償保険の必要性を検討します。
ただし、前述の通り、ADHDの方はこれらの保険への加入が難しい場合があるため、FPなど専門家への相談が不可欠です。 - 死亡保障については、残された家族の生活費や葬儀費用などを考慮し、必要な保障額を生命保険で準備します。
- 個人賠償責任への備え
- ADHDの特性(衝動性や不注意など)を考えると、他人への損害賠償リスクは無視できません。
個人賠償責任保険は比較的安価な保険料で高額な賠償に備えられるため、優先度は高いと言えます。
自動車保険や火災保険の特約として付帯できないか、まずは確認してみましょう。
- ADHDの特性(衝動性や不注意など)を考えると、他人への損害賠償リスクは無視できません。
- 将来の資金準備(個人年金保険など)
- 家計に余裕があれば、お子さん自身の老後資金の準備として個人年金保険を検討します。
具体的な組み合わせプラン例
ケース【1】成人当事者・就労中の方
- 基本:健康保険 + 自立支援医療制度
- 医療費の補足:引受基準緩和型医療保険(必要に応じて)
- 賠償リスク:個人賠償責任保険
- 収入保障:所得補償保険(加入できれば)、または貯蓄で備える
- 死亡保障:必要な保障額に応じて生命保険
ケース【2】ADHDのお子さんがいるご家庭
- 基本:お子さんの健康保険 + 子どもの医療費助成制度 + 自立支援医療制度
- 親の万が一:親御さんの生命保険(死亡保障)
- 賠償リスク:個人賠償責任保険(家族型)
- 教育資金:終身保険(被保険者:親御さん)または貯蓄(教育方針と家計状況に応じて)
公的制度は非常に手厚いものが多いですが、その内容は複雑で、多くの場合、自分で申請しなければ利用できません。まずは、お住まいの自治体の福祉窓口や、発達障害者支援センターなどに相談し、利用できる制度を正確に把握することが大切です。
その上で、FPに必要な保障について相談し、民間の保険を検討するのが良いでしょう
公的制度は「申請主義」と言われ、知っているかどうか、申請するかどうかで受けられるサポートに大きな差が出ることがあります。
ADHDの特性上、情報収集や複雑な手続きが苦手な方もいらっしゃるかもしれません。




家族の方でも複雑な手続きは大変だよ…。




手続きはご家族や支援者、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
ADHDでも保険に入れた!具体的な実例



ADHDのある方やそのご家族が、実際にどのように保険を選び、加入し、また時にはトラブルに直面しながらも解決してきたのか、具体的な事例を通して見ていきましょう。
これらの体験談は、きっとあなたの保険選びのヒントになるはずです。
ADHD診断後、一般の医療保険に加入できたケース
状況
Aさんは5年前にADHDと診断されました。
最近、住宅の購入を検討し始めたことをきっかけに、団体信用生命保険(住宅ローンを組む際に加入が求められることが多い生命保険)と、万が一働けなくなった時のための収入保障保険についてFPに相談しました。
告知内容
ADHDの診断名、長期間にわたる通院歴、服薬状況を正直に告知しました。
幸い、休職経験はなく、うつ病などの二次障害もありませんでした。
工夫した点
発達障害に詳しいFPに相談し、適切な告知方法についてアドバイスを受けました。
FPは、Aさんの状況を丁寧にヒアリングし、団体信用生命保険と合わせて、収入保障保険と就業不能保険の組み合わせを提案しました。
結果
銀行の団体信用生命保険の審査に通り、さらに収入保障保険と就業不能保険にも、健康な方と同じ保険料で加入することができました。
FPからのコメント
Aさんのように、ADHDと診断されていても、症状が安定していて日常生活に大きな支障がなく、二次障害もなければ、一般の保険に加入できる可能性は十分にあります。
大切なのは、正直な告知と、発達障害に理解のある専門家への相談です。



お子さんがASDで死亡保険に加入できたケース
状況
Bさん夫妻には、18歳になるASD(自閉スペクトラム症)のお子さんがいます。
お子さんのために加入していた保険が満期を迎えるにあたり、特に死亡保障についてFPに相談しました。
課題
ASDのお子さんの場合、ADHDのお子さんよりも保険の選択肢が少ない傾向があります。
また、多くの引受基準緩和型保険は20歳以上でないと加入できないという制約もありました。
工夫した点
FPは、告知項目が非常に少ないタイプの死亡保険を探し出しました。
その保険の告知項目は「過去5年以内にがんの検査などをしていないか」「身体に所定の障害がないか」の2点のみでした。
Bさんのお子さんの診断はASDのみで、これらの告知項目には該当しませんでした。
結果
10年間の保険料払込で、保障は一生涯続く死亡保険に無事加入することができました。
親御さんが保険料を全額負担することで、お子さんの将来に備えることができた事例です。
FPからのコメント
このケースのように告知項目が限定的な保険を選ぶことで、加入できることがあります。
加入後すぐの入院による保険金請求
状況
Cさんは発達障害の当事者です。
年末に医療保険とがん保険に加入しました。
翌年の2月、病気が見つかり、加入からわずか3ヶ月も経たないうちに入院することになりました。
結果
きちんと告知をして保険に加入していたため、入院給付金と入院一時金が問題なく支払われました。
FPからのコメント
Cさんのように、加入時に健康状態などを正直に告知していれば、たとえ加入後すぐに病気やケガで入院することになったとしても、保険金や給付金はきちんと支払われます。
これが、保険の正しい活用方法であり、正直な告知がいかに大切かを示しています。
告知義務違反トラブル事例と解決策
状況
Dさんは、保険の営業担当者に勧められるまま保険に加入しました。
その際、「発達障害は病気ではないから告知しなくても大丈夫だろう」と自己判断し、ADHDであることを告知しませんでした。しかし、後になって不安になり、発達障害専門のFPに相談しました。
問題点
FPが確認したところ、Dさんのケースは「告知義務違反」に該当する可能性が高いことが判明しました。
このままでは、万が一のことがあっても保険金が支払われなかったり、契約自体が解除されたりするリスクがありました。
対応策
FPのアドバイスを受け、Dさんは以下のいずれかの対応を検討しました。
- 現在加入している保険会社に、改めてADHDであることを告知し、再査定してもらう。
- 現在の契約はいったん整理し、ADHDであることを正直に告知した上で、新たに加入できる保険を探す。
Dさんは、これ以上不安な気持ちを抱えたくないとの思いから、2の「正直に告知した上で新たに加入できる保険を探す」ことを選択しました。
結果
発達障害に詳しいFPのサポートのもと、Dさんの状況や希望に合った保険を見つけ、無事に加入することができました。
FPからのコメント
「発達障害は病気じゃないから伝えなくていい」といった間違った情報や、保険の営業担当者からの正しくないアドバイスをそのまま信じてしまうのは、とても危険です。
Dさんのように、あとからでも正直に伝え直したり、正しい内容で保険に入り直したりすることが、将来の安心につながります。
また、ADHDの人やそのご家族にとって、正しい情報を手に入れるのがむずかしいこともあります。
だからこそ、信頼できる専門家に相談することがとても大切です。
保険の審査に落ちた体験談
状況
Eさんは、5歳になるお子さん(障害者手帳をお持ち)のために医療保険に申し込んだものの、残念ながら審査に通らなかったという経験をしました。
考えられる理由
お子さんが障害者手帳を持っていること、ADHDの症状の程度、他に併存している疾患の有無などが総合的に判断された結果、保険会社の引受基準を満たさなかった可能性が考えられます。
FPからのアドバイス
保険の審査に落ちてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まず、可能であれば保険会社に審査に通らなかった理由を確認してみましょう。
また、引受基準緩和型保険など、他の選択肢を検討することが大切です。
保険会社によって審査基準は異なりますので、複数の保険会社やFPに相談し、粘り強く情報収集を続けることをお勧めします。




これらの事例からわかるように、ADHDと保険を考える上では、正しい情報を得ること、正直に告知すること、そして諦めずに専門家へ相談することが非常に重要です。
生命保険のお悩み、ご相談下さい。
生命保険でこのようなことでお悩みではありませんか?



- 持病があって加入できないと言われたことがある
- 生命保険の見直しを検討しているが保険料をもっと安くしたい
- 1社だけではなく、複数の保険会社から比較して保険を選びたい
- どんな生命保険に加入すればいいのか分からない
もしも、生命保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
まとめ ADHDのある方が保険に入るには?加入のコツと実際の事例もご紹介



この記事では、ADHD(注意欠如・多動症)のある方やそのご家族が保険を検討する際に知っておくべき基本的な知識から、具体的な保険の種類、告知義務の重要性、公的制度との連携、そして実際の事例に至るまで、網羅的に解説してきました。
最後に、ADHDと保険について、押さえておくべき重要なポイントを改めて整理し、皆さんが次に取るべき具体的な行動について提案します。
ADHDと保険、押さえておくべき重要ポイント
- ADHDでも保険加入の道はある!
ADHDと診断されていても、諦める必要はありません。
正しい知識を持ち、適切な準備をすれば、保険に加入できる可能性は十分にあります。 - 告知義務は必ず守る
過去の病歴や現在の健康状態(診断名、通院歴、服薬状況、日常生活の状況など)を正直に、正確に保険会社に伝えることが、後々のトラブルを避けるための最も重要なステップです。 - 加入しやすい保険も検討する!
通常の保険への加入が難しい場合でも、引受基準緩和型保険や共済など、ADHDのある方が比較的加入しやすい選択肢もあります。ただし、保険料や保障内容をしっかり比較検討することが大切です。 - 公的制度を最大限に活用する!
障害年金、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療制度など、ADHDのある方が利用できる公的制度はたくさんあります。まずはこれらの制度をしっかりと理解し、活用した上で、不足する部分を民間の保険で補うという考え方が基本です。 - 一人で悩まず専門家に相談する!
保険の専門用語や制度は複雑で、ADHDの特性上、情報収集や手続きが難しいと感じることもあるかもしれません。そんな時は、一人で抱え込まず、発達障害に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)や保険代理店、またはお住まいの自治体の相談窓口や発達障害者支援センターなどに積極的に相談しましょう。
保険選びは、未来の安心をデザインする大切な一歩です。ADHDの特性を理解し、あなたに寄り添ってくれる専門家と一緒に、最適なプランを見つけてください。
私たちファイナンシャルプランナーは、そのお手伝いをするためにいます。
この記事が、ADHDのある方やそのご家族の皆さんの不安を少しでも和らげ、未来への希望を持つための一助となれば幸いです。