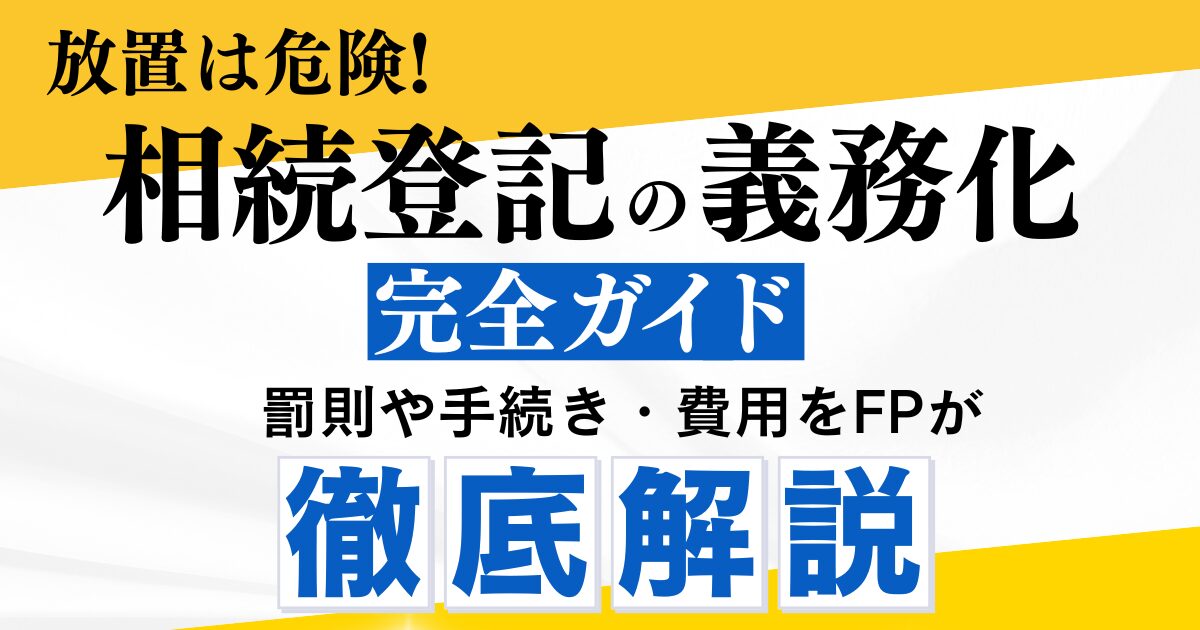相続登記が義務化されたって聞いたけど、何から手をつければいいか全然わからない…。
昔の相続も対象なんて、どうしよう…。




ご安心ください。この記事で義務化のポイントから具体的な手続きまで、一つひとつ丁寧に解説します。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
この制度改正により、
不動産を相続した場合は必ず登記手続きを行う必要があり、怠ると最大10万円の過料が科される可能性があります。
本記事では、相続対策の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)として、相続登記の義務化について分かりやすく解説します。
過去に発生した相続にも適用されるこの新制度について、期限や手続き方法、費用、さらには困った時の救済策まで、初心者の方でも安心して対処できる情報をご案内します。
この記事を読むことで、登記の義務化について以下のことがわかります。
- 義務化の内容と対象を正確に理解できる
- 具体的な期限と罰則を把握し、適切に対処できる
- 手続きの流れと必要書類が分かり、スムーズに進められる
- 費用の目安を知り、予算を立てられる
- 救済策や裏技を活用し、困難な状況を乗り切れる



相続のお悩み解決の第一歩
\ お気軽に無料相談ができます /



相続のお悩み解決の第一歩
\ お気軽に無料相談ができます /
相続登記の義務化とは?2024年4月からの変更点と背景







ここでは、制度の基本と、なぜ今義務化が必要になったのかを解説します。
相続登記の基本概念
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、登記簿に記録されている所有者の名義を相続人の名義に変更する手続きです。
具体的には以下の要素から構成されます。
- 相続:亡くなった方の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐこと
- 登記:土地・建物の所有者情報を法務局に登録すること
- 登記簿:不動産の権利関係を記録した公的書類
これまでは任意の手続きでしたが、2024年4月1日から法的義務となりました。
義務化の社会的背景
相続登記の義務化は、深刻化する所有者不明土地問題の解決を目的としています。
国土交通省の調査によると、この面積は日本の国土の約24%に達し、九州全体を上回る規模となっています。
この問題が引き起こす主な影響は以下の通りです。
- 公共事業の遅延:災害復興や都市開発で用地取得が困難
- 経済損失:年間数兆円規模の経済的損失
- 環境悪化:管理されない空き家・土地による景観・治安の悪化
所有者不明土地の最大の原因が相続登記の未完了であったため、国は法改正に踏み切りました。
義務化による主な変更点
今回の法改正で、相続登記の扱いは大きく変わりました。
主な変更点を表で確認しましょう。
| 項目 | これまで(任意) | 義務化後(2024年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 任意の手続き | 法的義務 |
| 期限 | なし | 相続を知った日から3年以内 |
| 罰則 | なし | 最大10万円の過料 |
| 対象 | 新規相続のみ | 過去の相続も含む |




特に重要なのは「過去の相続も含む」という点です。
心当たりがある方は、すぐにご自身の状況を確認する必要があります。
相続登記の期限はいつまで?罰則(過料)の詳細を解説







いつまでに手続きすればいいの?




もし遅れたらどうなる?
ここでは、具体的な期限と罰則の内容を詳しく見ていきます。
相続登記の具体的な期限
相続登記の期限は、
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
これをケース別に見てみましょう。
| 2024年4月1日以降に発生した相続 | 相続を知った日から3年以内に手続きを完了する必要があります。 |
| 2024年4月1日より前に発生した相続 | 2027年(令和9年)3月31日までに手続きを完了すればよいとされています。 |
罰則(過料)の内容
期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料の特徴は以下の通りです。
- 行政上のペナルティであり、刑事罰ではない
- 前科はつかない
- 期限超過後、まず法務局から催告通知が届く
- 催告後の指定期間内に登記すれば過料は科されない見込み




うっかり忘れても、すぐ罰金というわけではないんですね。少し安心しました…。




はい、その通りです。ただし、催告を無視すると過料の対象になります。通知が来たら速やかに対応することが肝心です。
罰則が免除される「正当な理由」とは
以下のような場合は、罰則が免除される可能性があります。
- 相続人が数十人など極めて多く、全員の把握に長期間を要する場合
- 遺言書の有効性や遺産範囲について裁判で争っている場合
- 本人が重病で手続きを行える状態にない場合
- DV被害者で避難中のため手続きが困難な場合
- 経済的困窮により登記費用を支払えない場合




実務上、正当な理由があることの証明責任は申請者側にあります。
罰則回避に頼るのではなく、まずは期限内の履行を目指すことが重要です
相続登記を放置する真のペナルティは過料ではなく、時間の経過とともに相続関係が複雑化し、手続きの費用や手間が雪だるま式に増大することです。
はじめてでも分かる!相続登記の手続き4ステップ
相続登記は、正しい手順で進めれば決して難しいものではありません。
ここでは、手続きの全体像を4つのステップに分けて解説します。




複雑に見える手続きも、一つずつ分解すれば大丈夫です。
この4ステップに沿って進めていきましょう。
まず、法的な相続人を確定するため、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて収集します。
収集が必要な戸籍の種類
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
2024年3月1日から開始された戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村役場でもまとめて取得可能になりました。
これは非常に便利な制度です。
相続人全員で不動産の分け方を決める遺産分割協議を行います。
協議では以下の点を決定します。
- 誰が何の不動産を相続するか
- 共有で相続する場合の持分割合
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印押印します。この書類が後の手続きで重要な役割を果たします。
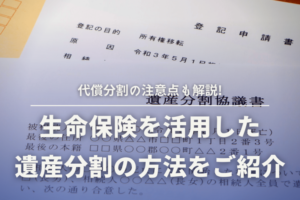
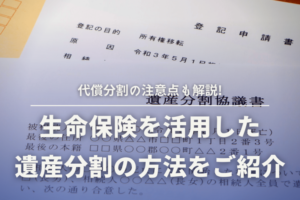
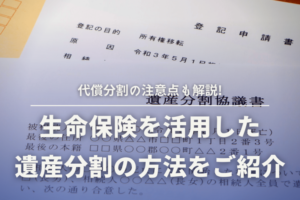
以下の表を参考に、ケースに応じた書類を準備してください。
【全ケース共通】
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 市区町村役場 | 相続人確定のため必須 |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 登記簿上の住所と死亡時住所の連結 |
| 相続人全員の現在戸籍謄本 | 各市区町村役場 | 生存証明 |
| 不動産取得者の住民票 | 市区町村役場 | 新名義人の住所証明 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 登録免許税計算用 |
| 登記申請書 | 自作または司法書士作成 | 申請のメイン書類 |
【遺産分割協議の場合】
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書 | 自作または専門家作成 | 全員の署名・実印必要 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各市区町村役場 | 実印証明 |
【遺言書がある場合】
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書 | 保管場所による | 自筆遺言は家庭裁判所の検認が必要な場合あり |
すべての書類を揃えたら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
主な申請方法
- 窓口への直接持参
- 郵送
- オンライン申請(専用ソフトと電子署名が必要)
申請後、書類に不備がなければ1~2週間程度で登記が完了し、登記識別情報通知が発行されます。
相続登記にかかる費用の内訳とシミュレーション



相続登記には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。




ここでは、必ず発生する実費と専門家への依頼費用に分けて、具体的な金額を解説します。
必ず発生する実費(登録免許税・書類取得費)
登録免許税
不動産の固定資産評価額の0.4%が課税されます。
なお、評価額100万円以下の土地については登録免許税の免除特例があります。
書類取得費用
戸籍や住民票などを取得するための手数料です。
| 書類 | 手数料(目安) |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 住民票・印鑑証明書 | 約300円 |
| 固定資産評価証明書 | 約300円 |
| 登記事項証明書 | 600円(オンライン請求で安価) |
相続人が多い場合や転籍が多い場合は、数千円から1万円を超えることがあります。
司法書士報酬の相場
相続登記を司法書士に依頼する場合の報酬相場は5万円~15万円程度です。
報酬に含まれる主なサービスは以下の通りです。
- 戸籍収集代行
- 遺産分割協議書作成支援
- 法務局への申請代理
不動産の数や相続人の数、関係の複雑さによって報酬額は変動します。



費用比較シミュレーション(自分でやる vs 司法書士依頼)
どのくらいの差が出るのか、具体的なモデルケースで比較してみましょう。
【前提条件】
- 固定資産評価額:2,000万円
- 相続人:3名
- 遺産分割協議で1名が相続
| 項目 | 自分で手続き | 司法書士依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 80,000円 | 80,000円 |
| 書類取得費用 | 約10,000円 | 約10,000円 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 約100,000円 |
| 合計 | 約90,000円 | 約190,000円 |




司法書士への依頼は約10万円の追加費用がかかりますが、これは「時間」と「安心」への投資です。
平日に役所へ行く時間が取れない方や、手続きに不安がある方は専門家への依頼を強くお勧めします。
期限に間に合わない時の救済策「相続人申告登記」とは




遺産分割の話し合いがまとまらなくて、3年の期限に間に合いそうにない…どうすればいいの?
ご安心ください。
そのような場合に備えて、罰則を回避できる救済策が用意されています。それが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記の概要とメリット・デメリット
相続人申告登記は、遺産分割協議が長引くなどの理由で期限内に正式な相続登記ができない場合の救済制度です。
この制度により、「私がこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申告することで、一時的に義務を履行したとみなされます。
メリット
- 手続きが簡単 相続人の一人から単独で申請可能
- 費用が安い 登録免許税不要
- 罰則回避 過料の対象にならない
デメリット
- 正式な登記ではない 所有権は確定しない
- 不動産処分不可 売却や担保設定ができない
- 二度手間の可能性 最終的に正式な登記が必要
- 個人単位の効力 申告した人のみ義務履行とみなされる
相続人申告登記の利用を検討すべきケース
以下のような状況で活用を検討してください。
- 遺産分割協議が難航し、合意の見通しが立たない場合
- 相続人が全国に散らばっており、協議が進まない場合
- 数次相続(相続が何代にもわたって発生)により相続人が膨大で、全員の同意取得が困難な場合
この制度は、責任感のある相続人が法的義務を果たしつつ、時間をかけて適切な解決策を見つけるためのセーフティーネットです。
不要な土地はどうする?相続土地国庫帰属制度を解説
相続した土地が、価値のない山林や利用価値のない土地だった場合、管理の負担だけが残ってしまいます。
そんな時に検討したいのが「相続土地国庫帰属制度」です。
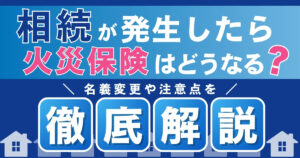
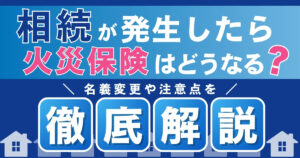
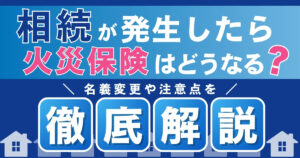
相続土地国庫帰属制度の概要
2023年4月27日から開始されたこの制度により、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能になりました。
この制度は、相続放棄をすると他の必要な財産(預貯金など)も失ってしまうという問題を解決し、不要な土地のみを手放す選択肢を提供します。
利用条件は非常に厳しい
ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。利用条件は非常に厳格です。
以下の土地は対象外となります。
- 建物がある土地(更地にする必要あり)
- 担保権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 境界が不明確な土地
- 崖や擁壁があり管理に過大な費用・労力がかかる土地
- 土壌汚染されている土地
- 工作物や車両などが放置されている土地
- 地下に埋設物がある土地
必要な費用(審査手数料と負担金)
制度の利用には費用がかかります。




この制度は「最終手段」と位置づけるべきです。
条件が厳しく費用も高額なため、まずは近隣への売却や自治体への寄付、専門業者への相談を検討しましょう。
相続登記の成功・失敗例から学ぶ!放置するリスクとは



相続登記を「まあ、いいか」と放置すると、将来的に大きなトラブルに発展することがあります。
ここでは、実際の失敗例からそのリスクを学びましょう。
成功ケース:相続人申告登記を賢く活用
状況
都内のAさん(40代)が地方の実家を3兄弟で相続。長男の海外赴任と次男との関係悪化により遺産分割協議が難航。
対応
期限が迫る中、司法書士に相談し「相続人申告登記」を活用。Aさんが単独で申告し、義務を履行。
結果
過料の心配から解放され、余裕を持って粘り強く協議を継続。1年後に協議がまとまり、正式な相続登記を完了。
失敗ケース:登記放置で売却チャンスを逃す
状況
Bさん(50代)が10年前に父親から山林を相続。「価値がないから」と費用を惜しんで登記を放置。
問題発生
近隣にリゾート開発計画が浮上し、高額買取の申し出が発生。しかし、登記名義が父親のままで売却不可。
複雑化
この10年間で叔父が死亡し、その子ども(従兄弟)も相続人に追加。疎遠な従兄弟からの実印取得が困難となり、売却チャンスを逸失。
教訓
初期の数万円を惜しんだことで、大きな機会損失が発生。
失敗ケース:数次相続で関係者が10人以上に
状況
Cさん(60代)の母親死亡時、実家の登記名義が30年前に死亡した祖父のままと判明。
問題の規模
祖父の相続(一次相続)から処理が必要に。すでに死亡した叔父・叔母の相続人も含め、関係者が10人以上に拡大。
結末
二世代分の相続手続きが必要となり、途方もない時間と費用が発生。一度の放置が雪だるま式に問題を拡大させる典型的な一例です。



相続のお悩み解決の第一歩
\ お気軽に無料相談ができます /



相続のお悩み解決の第一歩
\ お気軽に無料相談ができます /
相続登記義務化に関する よくある質問
ここでは、相続登記の義務化に関してよく寄せられる質問にお答えします。
まとめ 相続登記をしないと10万円の罰金!? 義務化でやるべき4つの対策
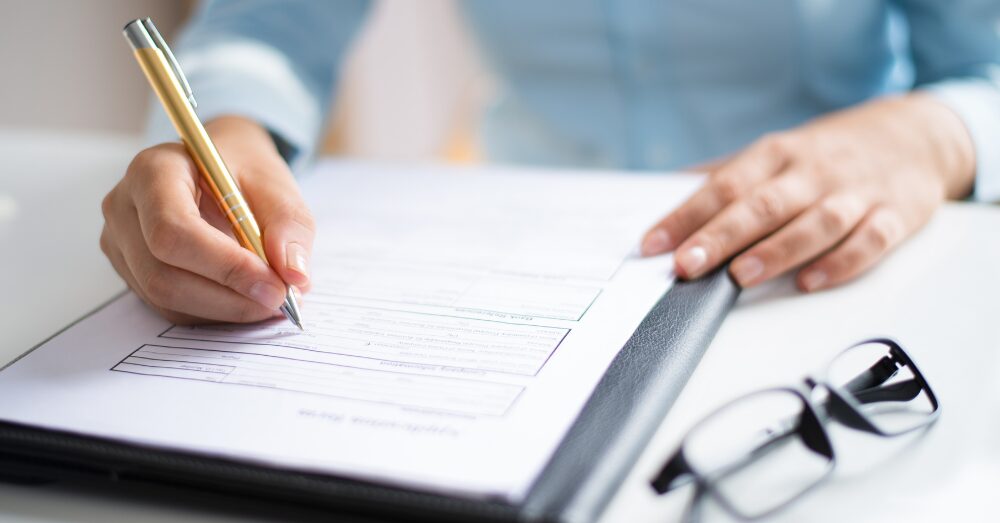
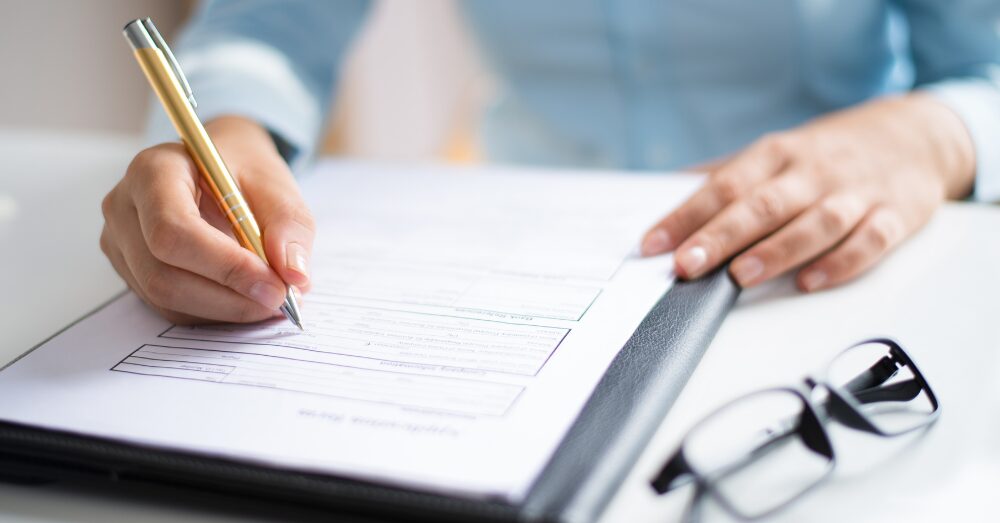
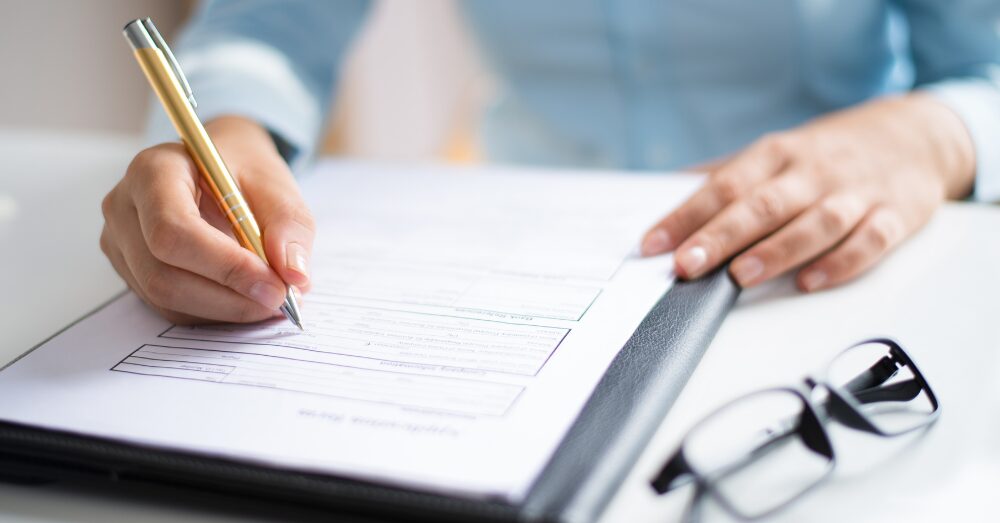
最後に、相続登記の義務化に関する重要ポイントを再確認し、次にとるべき行動を整理します。
重要ポイントの再確認
- 義務化の基本事項
- 2024年4月1日から法的義務化
- 過去の相続にも遡って適用
- 期限は「知った日から3年以内」
- 過去分は2027年3月31日までに完了
- 罰則と救済策
- 最大10万円の過料(前科はつかない)
- まず催告があり、対応すれば過料は回避できる可能性が高い
- 「相続人申告登記」による一時的救済策がある
- 手続きと費用
- 4ステップで進める(相続人確定→協議→書類準備→申請)
- 費用の目安は自分で約9万円、司法書士依頼で約19万円(個々のケースによる)
- 専門家への依頼は時間と安心を買う投資と考える
今すぐとるべき3つのアクション
この記事を読んだあなたがまず行うべき具体的なアクションは以下の通りです。
- 現状確認
心当たりのある不動産の登記事項証明書を取得し、現在の名義人を確認する。 - 期限の把握
該当する相続がある場合は、ご自身のケースでの期限を正確に計算する。 - 相談の検討
少しでも不安や不明点があれば、一人で抱え込まず専門家(法務局、司法書士など)に相談する。
何から始めればよいか分からない、家族との話し合いに不安があるという方は、弊社までご相談ください。
弊社では、あなたの状況を整理し、最適な解決策を見つけるサポートをします。
大切な家族の資産を守り、将来のトラブルを回避するため、今日から行動を始めましょう。