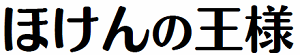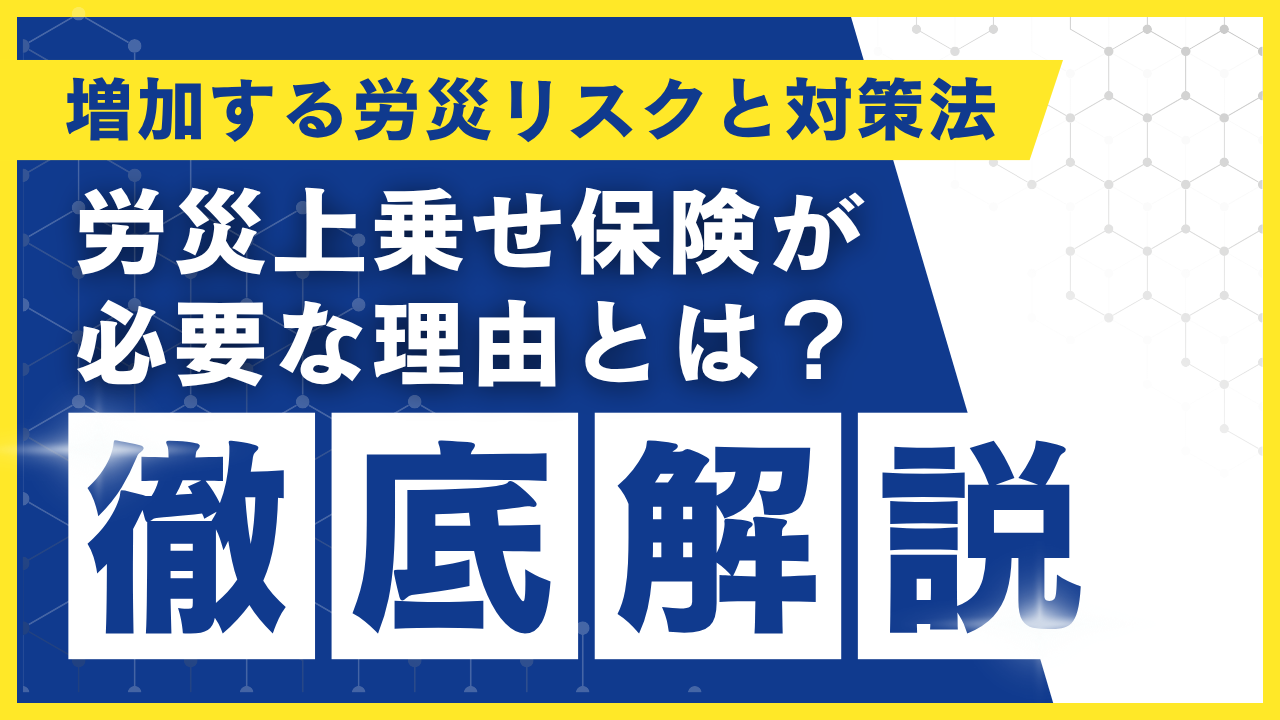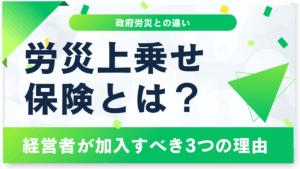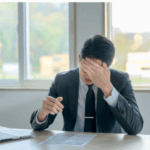 従業員
従業員社長、今朝のニュース見ましたか?取引先と同じくらいの規模の会社が、従業員さんの事故で1億円を超える賠償命令を受けたそうです。
政府の労災保険だけでは、とても足りなかったとか…。
うちは大丈夫でしょうか?
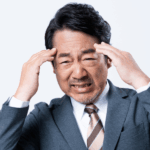
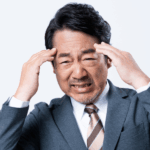
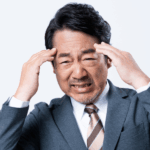
他人事ではないな。従業員の安全はもちろん第一だが、万が一の時に会社が傾くようなことがあっては、皆の生活を守れない。
政府の保険で十分だと思っていたが、一度しっかり調べる必要がありそうだ…。
このような会話は、多くの経営者様や役員の皆様が一度は心の中で交わしたことがあるのではないでしょうか。
日々、従業員の生活と会社の未来を背負い、事業に奮闘されている中で、「万が一」のリスクは常に頭の片隅にあるもの。
しかし、その「万が一」が、会社の存続そのものを揺るがすほどの破壊力を持つ可能性があることに、どれほどの方が気づいているでしょうか。
多くの方が、「従業員を一人でも雇っていれば、政府の労災保険に加入しているから大丈夫」と考えていらっしゃいます。
しかし、その認識は、現代の経営環境においては極めて危険な誤解と言わざるを得ません。
この記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)として数多くの企業のリスク管理に携わってきた専門家の視点から、なぜ政府の労災保険だけでは不十分なのか、そして、会社と大切な従業員を本当に守るために不可欠な「労災上乗せ保険」の必要性について、公的なデータと実際の事例を交えながら、徹底的に解説していきます。
中小企業向け
損害保険料削減のご案内
中小企業向けの損害保険で
お困りのことはありませんか?


- 建設業×賠償責任保険
保険料削減率 56.3%
保険料 311万円 → 136万円 - 製造業×火災保険・機械保険
保険料削減率 33.7%
保険料 228万円 → 151万円 - 運送業×自動車保険・運送保険
保険料削減率 35.5%
保険料 633万円 → 408万円
\ 複数の保険会社から御社のご要望に合わせた保険をご提案 /
複数の保険会社から
\ 御社のご要望に合わせた保険をご提案 /
政府の労災保険だけでは不十分な理由
本題に入る前に、この記事が最もお伝えしたい結論から申し上げます。
それは、「政府の労働者災害補償保険(労災保険)だけに頼ることは、重大な経営リスクを放置しているのと同じである」という事実です。
このリスクは、大きく分けて2つの側面から会社を襲います。
一つは、従業員やそのご遺族から提起される、数千万円から時には数億円にも上る高額な損害賠償請求です。
政府の労災保険は、治療費や休業中の一部の所得を補償してくれますが、事故によって生じた精神的苦痛に対する「慰謝料」や、将来得られたはずの収入「逸失利益」まではカバーしてくれません。
この不足分は、会社の責任が問われた場合、すべて企業が負担することになります。
もう一つは、被災した従業員の生活を十分に支えきれないことによる、信頼関係の崩壊です。
政府の補償だけでは、元の生活水準を維持することは困難な場合が多く、従業員やその家族は経済的にも精神的にも大きな不安を抱えることになります。
「会社は何もしてくれなかった」という不信感は、他の従業員の士気にも深刻な影響を及ぼし、企業の土台そのものを蝕んでいきます。
増加する労災リスクの実態とは
「うちの会社は安全なオフィスワーク中心だから」「長年、大きな事故は起きていないから大丈夫」――。
そうした考えが、いかに危険であるかを、客観的なデータと実際の裁判例をもとに解き明かしていきます。
ここからは、経営者が直視すべき3つの厳しい現実について、詳しく見ていきましょう。
増加する労働災害の発生状況
労働災害は、特定の危険な業種だけの問題ではありません。
厚生労働省の統計によれば、労働災害による休業4日以上の死傷者数は近年増加傾向にあり、直近のデータでは年間13万5,000人を超え、4年連続で増加しています。
| 休業4日以上の死傷災害 | 死傷者数(%) |
|---|---|
| 転倒 | 36,378(26.8%) |
| 動作の反動・無理な動作 | 22,218(16.4%) |
| 墜落・転落 | 20,699(15.3%) |
| はさまれ・巻き込まれ | 13,550(10.0%) |
| 切れ・こすれ | 7,420(5.5%) |
| 激突 | 6,947(5.1%) |
| その他 | 28,506(21.0%) |
事故の種類で最も多いのは「転倒」で、全体の約27%を占めます。
次いで「動作の反動・無理な動作(腰痛など)」、「墜落・転落」と続きます。
特に建設業や製造業では死亡災害や重篤な事故の割合が高いものの、「転倒」や「腰痛」はあらゆる業種で起こりうる事故です。


さらに見過ごせないのが、労働者の高齢化に伴うリスクの増大です。
60歳以上の労働者の死傷者数は高い水準で推移しており、労働災害発生率は30代と比較すると男性は約2倍、女性は約4倍にも達します。
日本の労働力人口に占める高齢者の割合が増加し続ける中、これまで「安全」だと考えられていた職場でも、事故のリスクは確実に高まっているのです。
10年前の安全管理の常識は、もはや通用しないと考えるべきでしょう。



企業の経営者様とお話ししていると、『うちはデスクワークだから労災は関係ない』というお声を時々耳にします。
しかし、データが示す通り、通勤途中の交通事故や、高齢従業員の転倒リスクは業種を問いません。
さらに、後述するメンタルヘルス不調のリスクを考慮すると、『安全な業種』というものは存在しないといえます。
政府労災保険の補償範囲の限界
政府の労災保険は、被災した労働者を保護するための非常に重要なセーフティネットです。
業務中や通勤中のケガや病気に対し、治療費(療養給付)や、休業中の所得の一部(休業給付として給付基礎日額の約8割)などが給付されます。
しかし、この制度には決定的な「穴」が存在します。それは、損害賠償における重要項目をカバーしていないという点です。
具体的には、以下の2つが挙げられます。
- 慰謝料
事故によるケガや後遺障害、あるいは死亡によって被った精神的・肉体的な苦痛に対する金銭的な補償です。
これは、被害者やその遺族の感情に寄り添う上で極めて重要な要素ですが、政府の労災保険の給付項目には含まれていません。 - 逸失利益(いっしつりえき)
もし事故がなければ、その人が生涯にわたって得られたはずの収入のことです。
政府労災から支給される障害(補償)給付や遺族(補償)給付は、あくまで一定の基準に基づいて計算されたものであり、被害者が失った将来の全収入を補填するものではありません。
では、この「穴」、つまり慰謝料や逸失利益の不足分は、誰が負担するのでしょうか。
答えは、「安全配慮義務に違反したと判断された企業」です。
従業員やその遺族が、政府労災の給付だけでは不十分だと考え、民事訴訟を起こした場合、裁判所が認定した賠償額から労災給付分を差し引いた差額のすべてを、会社が支払わなければならないのです。
多くの経営者が、政府の労災保険は「会社を守るための保険」だと誤解していますが、それは間違いです。
政府の労災保険はあくまで「被災した労働者の最低限の生活を守るための社会保障制度」であり、企業の経営リスクから守ってくれるものではないのです。
安全配慮義務違反による高額賠償の実例
企業が従業員に対して負う責任の中で、最も重いものの一つが「安全配慮義務」です。
この義務は非常に広範で、物理的な危険(機械の安全対策、作業場の整理整頓など)だけでなく、長時間労働の抑制やハラスメント防止といった、心身の健康を守るための配慮も含まれます。
そして、この義務を怠った結果、労働災害が発生したと裁判所に判断された場合、企業は極めて高額な損害賠償を命じられることになります。
過去の判例を見てみましょう。
- クレーン作業中の事故で従業員が重い後遺障害(頚椎損傷)を負ったケースでは、裁判所は会社に対し約1億6,500万円の支払いを命じました。
- 過労が原因で従業員が死亡した(過労死)ケースでは、会社と役員に対し約7,800万円の支払いが命じられています。
- 和解事例の中には、最高で2億4,000万円というケースも報告されています。
- 足の骨折で後遺障害11級というケースでさえ、5,000万円の損害賠償請求が起こされた事例もあります 15。
これらの金額は、中小企業にとって一回の事故で倒産に追い込まれかねない、まさに経営の根幹を揺るがす金額です。
自己資金や金融機関からの借入で対応できるレベルをはるかに超えており、保険による事前の備えがなければ、事業継続は不可能と言っても過言ではありません。
急増するメンタルヘルス不調による労災
近年、労働災害の様相は大きく変化しています。その象徴が、「精神障害」に関する労災請求の急増です。
厚生労働省の発表によると、精神障害の労災請求件数は年間3,780件で、支給決定件数も6年連続で過去最多を更新するなど、高止まりの状況が続いています。
その原因として最も多いのが、「上司等からのパワーハラスメント」です。
支給が決定された事案の中で、パワハラが原因とされた件数が突出して多くなっています。
かつては「職場の人間関係の問題」として片付けられていた事柄が、今や明確な「労働災害」として認定され、企業の安全配慮義務違反が厳しく問われる時代になったのです。
この「新型労災」は、従来の物理的な事故とは異なり、いくつかの点で企業にとってより大きなリスクをはらんでいます。
- 業種を問わない普遍性
建設現場の転落事故と違い、パワハラや過重労働はあらゆる業種のオフィスで起こりえます。 - 立証の難しさ
「安全な職場環境を提供していた」ことを企業側が証明するのは、物理的な安全対策に比べてはるかに困難です。目に見えないストレスや人間関係の問題は、管理が非常に難しい領域です。 - 高額賠償への発展
精神的な苦痛に対する慰謝料が高額になる傾向があり、自殺などの最悪のケースに至った場合、賠償額は1億円を超えることも珍しくありません。
かつての「安全な職場」の定義が、物理的な安全確保から、心理的な安全確保へと大きく広がったことです。
この変化を認識せず、旧来の感覚で労務管理を行っている企業は、気づかぬうちに巨大な賠償リスクを抱え込んでいるのです。
ここで、政府の労災保険と、それを補う上乗せ保険の役割の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 政府労災保険 | 労災上乗せ保険 |
|---|---|---|
| 目的 | 労働者の最低限の生活保障 | 政府労災の不足分補填、企業の賠償リスク対策 |
| 加入 | 強制 | 任意 |
| 治療費 | 補償される | 上乗せ補償が可能 |
| 休業補償 | 給与の約8割 | 上乗せ補償が可能 |
| 慰謝料 | 対象外 | 使用者賠償責任保険で補償 |
| 逸失利益 | 一部のみ補償 | 使用者賠償責任保険で補償 |
| 訴訟費用・弁護士費用 | 対象外 | 使用者賠償責任保険や弁護士費用補償特約で補償 |
| 死亡・後遺障害 | 定められた基準額 | 慰謝料を含めた賠償金や、上乗せの補償金に対応 |
政府の労災保険が「治療」と「当面の生活」を支えるものであるのに対し、労災上乗せ保険は、そこから先の「元の生活への回復支援」と「会社の法的・経済的リスクからの防御」という、二つの重要な役割を担っているのです。
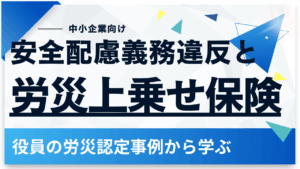
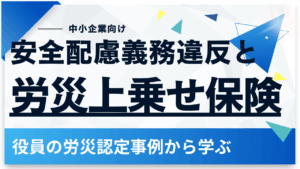
建設業向け
損害保険料削減のご案内
複数の保険会社から保険料・補償内容を徹底的に比較して、保険料削減案をご提案いたします。


- 賠償責任保険 保険料削減例
約77%割引 - 労災上乗せ保険 保険料削減例
約66%割引 - 建築・土木・組立工事保険料 保険料削減例
約52%割引
一例です。ご契約の条件により保険料が異なります。
\ 複数の保険会社から御社のご要望に合わせた保険をご提案 /
複数の保険会社から
\ 御社のご要望に合わせた保険をご提案 /
労災上乗せ保険の具体的な活用方法
では、これらの深刻なリスクに対して、企業は具体的にどう対処すればよいのでしょうか。
その答えが「労災上乗せ保険(業務災害補償保険)」への加入です。
しかし、ただ加入すれば良いというものではありません。自社の状況に合わせて、必要な補償を過不足なく備えることが重要です。
ここでは、労災上乗せ保険の仕組みと、事業形態別の賢い活用法を解説します。
労災上乗せ保険の2つの補償内容
労災上乗せ保険は、大きく分けて2つの補償から成り立っています。
法定外補償保険(ほうていがいほしょうほけん)
これは、従業員の福利厚生を充実させるための補償です。
政府の労災保険から給付される金額に「上乗せ」して、会社独自の補償を行うための原資となります。
例えば、
- 休業補償
政府労災の約8割給付に会社が2割を上乗せし、休業中の補償を100%にする。 - 死亡・後遺障害補償
政府労災の給付とは別に、会社の弔慰金・見舞金規定に基づき、追加の一時金を支払う。
このような手厚い補償は、被災した従業員やその家族に「会社が親身になって支えてくれている」という安心感を与え、感謝の気持ちを育みます。
結果として、高額な損害賠償請求訴訟へと発展する可能性を低減させる効果も期待できます。
使用者賠償責任保険(しようしゃばいしょうせきにんほけん)
こちらは、会社の経営そのものを守るための補償です。
万が一、従業員やその遺族から安全配慮義務違反などを理由に訴訟を起こされ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、その賠償金をカバーします。
補償の対象となるのは、
- 慰謝料
- 逸失利益
- 訴訟費用や弁護士費用
1億円を超えるような高額賠償命令が出た際に、会社の資産を守り、倒産を防ぐための最後の砦となるのが、この使用者賠償責任保険なのです。
この2つの補償は、まさに車の両輪です。まず『法定外補償』で従業員への手厚いケアという”心”を示し、信頼関係を築く。
これが第一の防御ラインです。
しかし、それでも訴訟リスクがゼロになるわけではありません。その万が一に備えるのが『使用者賠償責任』という”鎧”です。
この両面があって初めて、真のリスク管理と言えるのです。
事業形態別の最適な加入方法
労災上乗せ保険への加入方法は、企業の規模や業種によって最適なルートが異なります。
中小企業の場合
最も効率的でコストメリットが大きいのは、商工会議所などが提供する団体制度を活用する方法です。
全国の会員企業がまとまることでスケールメリットが働き、個人で加入するよりも大幅に割引された保険料(最大で58%割引などの例も)で加入できます。
プラン内容も中小企業に共通するリスクを想定して設計されていることが多く、選択しやすいのが特長です。
保険会社や保険商品によって利用できる団体が異なりますので、保険会社や保険代理店へ確認をしましょう。
また、これまで加入している保険代理店を通じて契約することが可能ですので、事務手続きにおいて不便になることはありません。
利用できる団体制度
- 商工会議所
- 商工会
- 中央会
- 法人会
- 建設業互助会など
一人親方(個人事業主)の場合
一人親方の方は、まず大前提として「元請け会社の労災保険は適用されない」という事実を認識しなければなりません。
一人親方は労働者ではなく事業主であるため、自ら国の労災保険に特別加入するか、民間の保険会社にて労災上乗せ保険(業務災害補償保険)を契約する必要があります。
特別加入制度とは、通常は労働者のみが対象となる労災保険に対して、一人親方などの個人事業主が任意で加入できる制度です。
加入の手続きは、「一人親方団体」と呼ばれる協会や組合を通じて行うのが一般的です。
一方、民間の業務災害補償保険は、補償内容や保険金額を柔軟に設計できるのが特長です。
たとえば、入院・通院の保障、休業中の所得補償、さらには業務外のケガに備えられる商品などもあります。
建設業の場合
建設業は全産業の中でも労働災害の発生率が高く、特に墜落・転落事故が後を絶ちません。このため、近年では大手ゼネコンをはじめとする元請会社が、下請会社に対して労災上乗せ保険への加入を契約の条件とすることが一般的になっています。
加入していないと、そもそも仕事を受注できないケースが増えているのです。
また、公共工事の入札に参加する際に企業の経営状況を評価する「経営事項審査」においても、労災上乗せ保険への加入は加点評価の対象となります。
もはや建設業にとって労災上乗せ保険は、単なるリスク対策ではなく、事業機会を確保し、拡大するための必須ツールへと変化しているのです。
保険料の税務上のメリット
労災上乗せ保険の保険料は、役員や特定従業員のみを対象とするような場合を除き、全従業員を対象とする福利厚生目的の費用として、法人税法上「損金」として全額経費計上することが認められています。これは、支払った保険料の分だけ会社の利益が圧縮され、結果として法人税の負担が軽減されることを意味します。
例えば、法人税率が30%の会社が年間30万円の保険料を支払った場合、実質的な負担額は「30万円 × (1 – 0.3) = 21万円」と考えることができます。
この節税効果により、見た目の保険料よりも少ない負担で、大きな安心を手に入れることができるのです。
現代のリスクに対応する特約
現代の労災リスクに対応するためには、基本の補償に加えて、「特約(オプション)」を付帯することが不可欠です。
以下の2つは、すべての企業が検討すべき重要な特約と言えます。
雇用慣行賠償責任補償特約
これは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、不当解雇、差別など、雇用に関するトラブルによって従業員から訴えられ、会社が法律上の賠償責任を負った場合の損害を補償する特約です。
精神障害の労災認定原因のトップがパワハラである現状を踏まえれば、この特約はもはや「標準装備」と考えるべきでしょう。
精神障害・心疾患補償特約
従業員のうつ病などの精神障害や、過労による脳・心臓疾患が、業務に起因するものとして政府の労災認定を受けた場合に、上乗せの補償金を支払う特約です。
これらの疾病は、業務との因果関係の判断が難しく、労災認定のハードルが高い側面がありますが、認定された場合の企業への影響は甚大です。
この特約を付けておくことで、複雑化する現代の労災リスクにも確実に対応できます。
実際の事例から学ぶ 労災上乗せ保険
これまでデータや法律の観点から解説してきましたが、ここでは具体的なケーススタディを通じて、労災上乗せ保険の有無が企業の運命をどう分けるのかを、よりリアルに感じていただきたいと思います。
成功事例 建設現場での転落事故
A社は、従業員15名の小規模な建設下請会社。
ある日、ベテラン職人のBさんが、高さ5メートルの足場から誤って転落し、腰の骨を折る重傷を負ってしまいました。
A社の社長は、以前から元請会社に勧められ、商工会議所の団体制度で労災上乗せ保険に加入していました。
事故発生後、社長はすぐに保険会社に連絡。A社の保険には「法定外補償」と「使用者賠償責任」の両方が付帯されていました。
対応と結果
・迅速な補償
政府の労災保険から休業給付(給与の約8割)が支払われるのに加え、A社が加入していた「法定外補償」から上乗せの休業補償が支払われ、Bさんの収入は100%確保されました。さらに、会社の規定に基づき、入院見舞金としてまとまった金額が保険から支払われました。
・信頼関係の維持
手厚い補償を受けたBさんとその家族は、「会社がここまでしてくれて本当にありがたい」と深く感謝。
治療とリハビリに専念することができ、訴訟などを考えることはありませんでした。
・事業への影響なし
元請会社への報告もスムーズに進み、A社の迅速で誠実な対応はかえって評価を高めました。
使用者賠償責任保険があったため、万が一の訴訟にも備えがあり、社長は安心して事業を継続できました。
このケースでは、労災上乗せ保険が、被災した従業員の生活を守ると同時に、会社の信用と財産を守り、未来へとつなぐ役割を果たしたのです。
失敗事例 IT企業での精神障害
C社は、急成長中のITベンチャー企業。優秀なプログラマーだったDさん(20代)は、連日深夜に及ぶ長時間労働の末、うつ病を発症してしまいました。
C社の社長は、「うちはオフィスワークだし、政府の労C社の社長は、「うちはオフィスワークだし、政府の労災保険に入っているから」と、上乗せ保険の必要性を感じていませんでした。
対応と結果
- 労災認定と訴訟
労働基準監督署は、Dさんのうつ病を長時間労働が原因の「業務上の災害」と認定。
Dさんには政府の労災保険から休業補償給付などが支払われることになりました。
しかし、将来のキャリアを絶たれ、精神的に追い詰められたDさんとその家族は、「会社の安全配慮義務違反が精神障害を招いた」として、C社を相手取り、慰謝料や逸失利益など1億2,000万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。 - 高額賠償命令
裁判所は、C社の極端な長時間労働を問題視し、安全配慮義務違反を認定。慰謝料や逸失利益などを含め、9,000万円の支払いを命じました。 - 会社の危機
政府の労災保険は、この賠償金には一円も使えません。
C社は、運転資金を取り崩し、多額の借金をして賠償金を支払うしかありませんでした。
資金繰りは一気に悪化し、優秀な人材は会社の将来を不安視して次々と流出。事業の継続自体が危ぶまれる事態に陥りました。
「保険料がもったいない」という僅かなコストを惜しんだ結果、C社は従業員の心身の健康と会社の未来という、取り返しのつかない代償を支払うことになったのです。
トラブル事例 労災隠しの末路
E社は、従業員30名の小さな製造工場。作業中に従業員のFさんが、機械で指に軽い切り傷を負いました。
労災事故が続くと保険料が上がることを懸念した現場の管理職は、Fさんに「会社の評判に傷がつくから、今回は自分の健康保険で病院に行ってくれないか」と頼み込みました。Fさんは断り切れず、その場は了承しました。
対応と結果
「労災隠し」の発覚
しかし、傷の治りが悪く、通院が長引くにつれてFさんは不満を募らせていきました。そして、同僚に相談した結果、労働基準監督署に「会社が労災を隠している」と通報しました。
厳しいペナルティ
監督署の調査が入り、E社の「労災隠し」はすぐに発覚。会社は労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金という刑事罰を受け、前科がつくことになりました。さらに、過去に遡って労災保険料と追徴金を支払うよう命じられました。
信頼の失墜
「労災隠し」の事実は社内に瞬く間に広まり、従業員たちは「この会社は自分たちを守ってくれない」と強い不信感を抱きました。職場の雰囲気は最悪になり、生産性も低下。Fさんはもちろん、他の従業員の離職も相次ぎました。
目先の保険料を気にした安易な判断が、刑事罰、追徴金、そして従業員からの信頼失墜という、何倍にもなって返ってくる最悪の結果を招いたのです。
労災隠しは、いかなる理由があっても絶対に行ってはならない犯罪行為となります。
中小企業向け
損害保険料削減のご案内
中小企業向けの損害保険で
お困りのことはありませんか?


- 保険料が毎年のように上がり続けて困っている。今すぐに保険料を削減したい。
- 同じ補償のまま 固定費を圧縮した成功事例を知りたい!
- 複数の保険会社の見積りを一括比較して選びたい!
- 決算対策に合わせ保険料の即時コスト計上を検討したい。
\ 複数の保険会社から御社のご要望に合わせた保険をご提案 /
複数の保険会社から
\ 御社のご要望に合わせた保険をご提案 /
よくある質問
ここまでお読みいただき、労災上乗せ保険の重要性をご理解いただけたかと思います。最後に、経営者の皆様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。
まとめ 労災上乗せ保険が必要な理由とは?増加する労災リスクと対策法を解説
この記事では、政府の労災保険だけでは対応しきれないリスクがあることを、公的なデータや実際の裁判例をもとにご紹介してきました。
「安全配慮義務」という重い責任、そしてパワハラや過労といった「現代型労災」の増加は、もはやどの企業にとっても他人事ではありません。
その致命的なギャップを埋め、会社と従業員を真に守るための唯一かつ最善の「労災上乗せ保険」です。
従業員の生活を手厚く支える「法定外補償」と、万が一の訴訟から会社の財産を守る「使用者賠償責任保険」。
この2つの機能を備えた上乗せ保険は、もはや単なる経費ではなく、事業の継続性、従業員との信頼関係、そして企業の社会的責任を全うするための、極めて重要な戦略的投資なのです。
まずは、貴社の現在のリスク状況を客観的に把握することから始めましょう。
従業員の年齢構成、業務内容、そして万が一の際に会社が負担できる財務的体力はどのくらいでしょうか。
その上で、自社に最適な補償内容を検討することが不可欠です。
しかし、多くの保険商品から最適なプランを自力で選ぶのは困難です。弊社では、貴社の状況を丁寧にヒアリングし、リスクを正確に診断した上で最適な保険プランをご提案する無料相談を実施しております。専門家の視点から、無駄なく、かつ十分な備えを構築するお手伝いをいたします。